発達障害のメカニズムとは?
発達障害とは、脳の機能や発達の仕方に何らかの特性があることで、社会性・注意力・感覚・行動・学習などで独自の傾向が現れる状態です。
「脳の器質的な問題」や「育て方の問題」と誤解されることがありますが、実際には先天的な神経発達のアンパランスや脳の情報処理に違いが生まれているというのが、主な原因です。
脳の神経ネットワークの偏り
発達障害と言われる根本には、脳内の神経ネットワークの働きに「ズレ」や「アンバランス」があります。
このズレは、以下のような神経のつながりの違いによって起こります。
・過剰に強いつながり(ハイパーコネクティビティ)
→感覚や注意に過敏になりやすく、周囲の刺激に圧倒されてしまう。
・過剰に弱いつながり(ハイポコネクティビティ)
→感情のコントロールや、他人との共感、マルチタスクが苦手になる傾向。
こうしたネットワークの「強すぎる」「弱すぎる」バランスの崩れが、ADHD、自閉スペクトラム、学習障害などの特性に関連しているとされます。
感覚処理の違い
発達障害の多くの方に共通するのが、感覚の処理の仕方の違いです。
脳が外部からの感覚情報(光、音、触覚、匂い、動き)を「過敏」または、「鈍感」に処理してしまうため、日常生活に支障が出やすくなります。
例:
・音や光に過剰に反応→ 集中が切れやすい、パニックになりやすい
・触覚に過敏→ 洋服のタグや肌触りが気になる
・感覚が鈍い→ 怪我に鈍感になる、ボディイメージが不安定
これらは、脳幹や小脳、前庭系(バランスをとる脳の部分)の機能異常と関連しているとされています。
自律神経とホルモンの関与
何らかの障害がある方は、自律神経(交感神経・副交感神経)の調整が自分の内側で調整することが難しくなっていることがあります。
これは神経系が常に「緊張状態」になりやすく、以下のような身体的な不調にもつながります。
・睡眠の質が悪い(夜なかなか眠れない)
・腸の動きが負担てい(便秘や下痢)
・呼吸が浅い、過呼吸傾向
・疲れやすく、電池が切れるように動かなくなる
また、ホルモンバランス(セロトニンやドーパミンなどの神経伝達物質)も関係しています。
例えは、ADHDではドーパミンの働きが弱いため集中力を維持しづらいと言われています。
発達のタイミングとズレ
「できること」と「できないこと」の差が大きく、これを「発達のアンバランス」とも言われます。
例えば、
・言葉は早いけど、感情のコントロールが苦手
・計算は得意だけど、文章題や日常会話が苦手
・細かい作業は得意でも、全体像が見えていない
これは、脳の一部が年齢よりも早く発達し、別の部分が遅れいていることにより起こします。
「これが、できるのになぜこれができないのか?」という周囲の誤解や本人否定につながってしまうこともあります。
カイロプラクティックから見た発達障害の視点
カイロプラクティックでは、神経の流れ=「脳と体の情報伝達の道」に着目します。
脳のネットワークの偏りや自律神経のの不安定さは、背骨のゆがみによる神経干渉(サブラクセーション)によって増幅する可能性があります。
カイロプラクティックは、「発達障害を治すものではありません」が、子ども本人の「本来の力」を引き出すための土台づくりとして役立つ可能性があります。
脳の配線が違うだけあり、能力がないわけでもありません。
大切なのは、その子の「特性」を理解し、どうすればその力を引き出せるのかを考えることです。
神経の流れをととのえて、感覚や姿勢、ストレス反応をサポートするカイロプラクティックは子供がより生きやすくなる「環境整備の一つ」として、役立ててください。




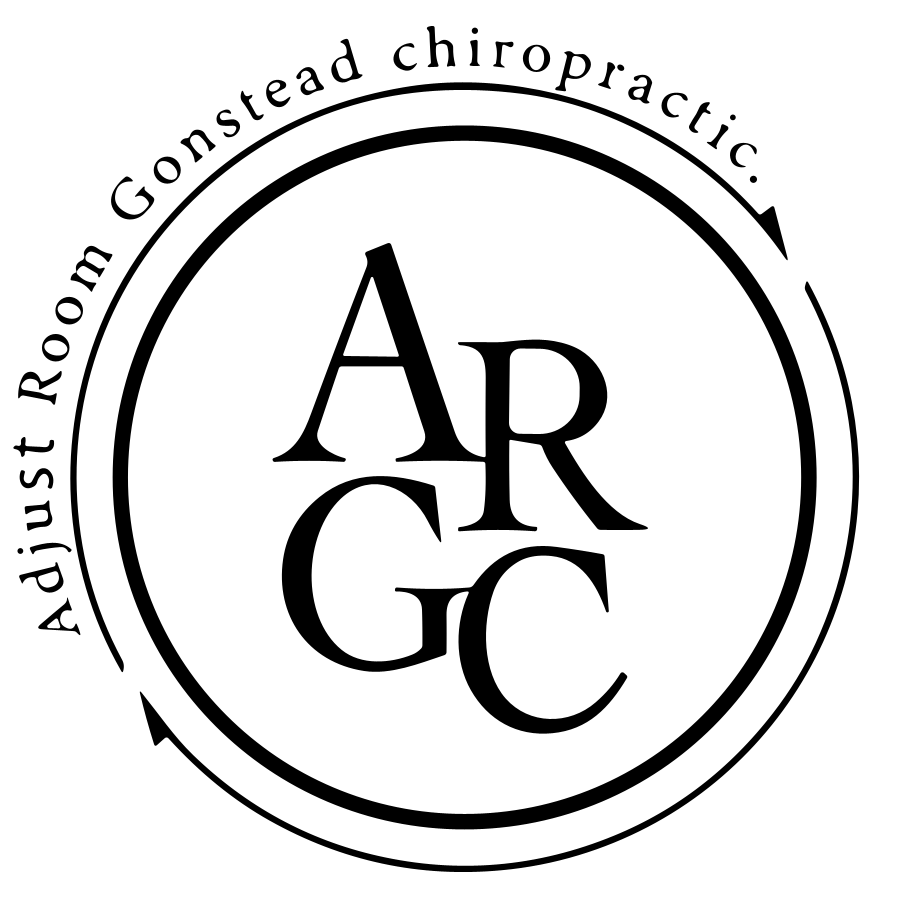


コメント